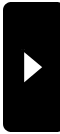作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせ
町田市で作曲家やってるTomです。毎月開催の、作曲を学ぶ&楽しむ会のおしらせ。
第61回。しめきりは5月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-61
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ソ短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
今回は、オイラも作品提出。『おおむね順調〜It’s Going Well』。ピアノ独奏。
第30回では;『踏み出す一歩 Foot To Step Out』、ピアノ独奏。
『おおむね順調』では、意識して、この作品とは対比的な内容をねらった。
そのうち公開予定である。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
初参加者より、「おもったよりアット・ホーム」との感想を、いただく。
たしかに。
オンラインゆえ、史上初めて、だれもがリアルにアット・ホームぢゃ。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
第61回。しめきりは5月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-61
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ソ短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
今回は、オイラも作品提出。『おおむね順調〜It’s Going Well』。ピアノ独奏。
第30回では;『踏み出す一歩 Foot To Step Out』、ピアノ独奏。
『おおむね順調』では、意識して、この作品とは対比的な内容をねらった。
そのうち公開予定である。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
初参加者より、「おもったよりアット・ホーム」との感想を、いただく。
たしかに。
オンラインゆえ、史上初めて、だれもがリアルにアット・ホームぢゃ。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
タグ :勉強会
2025年05月13日 Posted by Tom Motsuzai at 11:00 │Comments(0)
健康意識と健康知識
町田市で作曲家やってるTomです。トーシツ制限について理解を深めたくて、手にした本。
以下、そのレビューをば。
***
坪井貴司・寺田新『よく聞く健康知識、どうなってるの?』(東京大学出版会、2025年)
斜め読みするだけなら、アレコレどっからでも手に入る、健康向上&維持に関する話題。その媒体がなんであれ、読みとき能力(=リテラシー)を高めるには、じっさいのところ、どこまでわかってるか/わかってないか、つまり留保&条件について自覚しておいた方がいい。
この一冊は、健康の2大テーマたる食事と運動に関するどの章も、教わりやすい語り口ではじめられている(後述)。開いてよかったと、思う。おかげで、健康意識高めではあっても、目移りするばかりのさまざまな健康知識へ、おいそれとは飛びつかなくなりそうだ。
要となる健康のバロメーターは、いわずとしれた体重。したがって、食餌療法の「ダイエット」が、あちこちで言及される。一方、常日頃口にするものもまた、「ダイエット(=常食)」がもつ含義。単に、肥満に対する摂食コントロールのみを、「ダイエット」は指すわけではない。
第1章の糖質制限食が、体重コントロールとしてのみ言及されているのは、「常食」としてのダイエット観が抜け落ちているせいではないか。
また、「不健康なジャンクフード(坪井・寺田 2025:65)」が、健康への悪影響として前提視されている。ここは、なぜ不健康なのかを、ぜひ問うてほしかった。すると各種ジャンクフードは、飲料であれ固形物であれ、おしなべて糖質過剰で(各種メガ盛りを思い合わせよ)、それこそが不健康の原因だと、浮き彫りにできたろう。
ここから糖質の制限は、体重コントロールのみならず、それ自体が健康に資する常食=ダイエットだと、さらに突っ込めたはず。
学生への講義との体裁で、運動部に所属する学生からの質問をきっかけに、はじめられる章も多い。大学出版会ならではだが、でも運動部って、そんな食事にばかり気を使ってるの?健康意識というかたちで、そもそものスポーツ(含筋トレ)よりも摂食に重きが置かれるのって、なんか不自然。
さいごに健康に関する知識は、ローカルかつグローバルな食文化を、「健康」の一言で、ただ一色に塗りつぶしてしまう。なかば、食べる薬。常食は、いわば身体と文化の接点。そんな文化の香りが、多少なりとも行間から漂ってほしかったところ。
以下、そのレビューをば。
***
──レビュー企画用献本御礼──
坪井貴司・寺田新『よく聞く健康知識、どうなってるの?』(東京大学出版会、2025年)
斜め読みするだけなら、アレコレどっからでも手に入る、健康向上&維持に関する話題。その媒体がなんであれ、読みとき能力(=リテラシー)を高めるには、じっさいのところ、どこまでわかってるか/わかってないか、つまり留保&条件について自覚しておいた方がいい。
この一冊は、健康の2大テーマたる食事と運動に関するどの章も、教わりやすい語り口ではじめられている(後述)。開いてよかったと、思う。おかげで、健康意識高めではあっても、目移りするばかりのさまざまな健康知識へ、おいそれとは飛びつかなくなりそうだ。
要となる健康のバロメーターは、いわずとしれた体重。したがって、食餌療法の「ダイエット」が、あちこちで言及される。一方、常日頃口にするものもまた、「ダイエット(=常食)」がもつ含義。単に、肥満に対する摂食コントロールのみを、「ダイエット」は指すわけではない。
第1章の糖質制限食が、体重コントロールとしてのみ言及されているのは、「常食」としてのダイエット観が抜け落ちているせいではないか。
また、「不健康なジャンクフード(坪井・寺田 2025:65)」が、健康への悪影響として前提視されている。ここは、なぜ不健康なのかを、ぜひ問うてほしかった。すると各種ジャンクフードは、飲料であれ固形物であれ、おしなべて糖質過剰で(各種メガ盛りを思い合わせよ)、それこそが不健康の原因だと、浮き彫りにできたろう。
ここから糖質の制限は、体重コントロールのみならず、それ自体が健康に資する常食=ダイエットだと、さらに突っ込めたはず。
学生への講義との体裁で、運動部に所属する学生からの質問をきっかけに、はじめられる章も多い。大学出版会ならではだが、でも運動部って、そんな食事にばかり気を使ってるの?健康意識というかたちで、そもそものスポーツ(含筋トレ)よりも摂食に重きが置かれるのって、なんか不自然。
さいごに健康に関する知識は、ローカルかつグローバルな食文化を、「健康」の一言で、ただ一色に塗りつぶしてしまう。なかば、食べる薬。常食は、いわば身体と文化の接点。そんな文化の香りが、多少なりとも行間から漂ってほしかったところ。
2025年04月24日 Posted by Tom Motsuzai at 08:30 │Comments(0)
作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせ
町田市で作曲家やってるTomです。毎月開催の、作曲を学ぶ&楽しむ会のおしらせ。
第60回。しめきりは4月30日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-60
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ド長調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
第30回の作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせでやったように、今回は第60回記念、丸5年。
ふたたび寸評者も、作品提出します。もちろん、自作に寸評をつけた上、公開。
前回同様、そのあとのZOOMを利用した質問会も、聴講を開放(要参加申込み)。無料。
*
第30回では、ラ短調の旋律課題だった。
今回は、その平行長調、ド長調。調号は共通していて、どちらも調号なし。
ここには、第30回と第60回をセットで提示する、作品意識がある。
ちなみに、旋律課題をこねくり回しながら、自分でも作品提出することを意識していなかったか?
↑もっともな疑問である。
だがそれよりも、旋律課題として適当かつ、これまでやってない試みを盛り込むのに、意を注いだ。
たった2小節でも、工夫のしがいはいくらでもある。これがすでに、作曲のはじまり。
つまり、複数のレヴェルで、創作は遂行されている。いわく;
・2小節の旋律
・第30回と第60回をセットとして提示する工夫
・この旋律課題を用いた16小節の作品
大事なのは、同じことをしないこと。なんらかの新味が、つねに求められる。
第60回。しめきりは4月30日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-60
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ド長調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
第30回の作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせでやったように、今回は第60回記念、丸5年。
ふたたび寸評者も、作品提出します。もちろん、自作に寸評をつけた上、公開。
前回同様、そのあとのZOOMを利用した質問会も、聴講を開放(要参加申込み)。無料。
*
第30回では、ラ短調の旋律課題だった。
今回は、その平行長調、ド長調。調号は共通していて、どちらも調号なし。
ここには、第30回と第60回をセットで提示する、作品意識がある。
ちなみに、旋律課題をこねくり回しながら、自分でも作品提出することを意識していなかったか?
↑もっともな疑問である。
だがそれよりも、旋律課題として適当かつ、これまでやってない試みを盛り込むのに、意を注いだ。
たった2小節でも、工夫のしがいはいくらでもある。これがすでに、作曲のはじまり。
つまり、複数のレヴェルで、創作は遂行されている。いわく;
・2小節の旋律
・第30回と第60回をセットとして提示する工夫
・この旋律課題を用いた16小節の作品
大事なのは、同じことをしないこと。なんらかの新味が、つねに求められる。
いつもとちがうことをやってみよう。
タグ :勉強会
2025年04月04日 Posted by Tom Motsuzai at 10:00 │Comments(0)
誕生日ランチについて語りまくる
町田市で作曲家やってるTomです。たべたケーキを寸評風にでやったことを、今回は、とあるレストランでいただいたコースで。グンとボリュームアップ!
*
お店:イル・リストランテ ニコ・ロミート(ブルガリ・ホテル・トーキョー内)
監修:ニコ・ロミート氏(アブルッツォ州出身)
ミシュランガイド:1つ星
ヘッドシェフ:マウロ・アロイシオ氏(ロンバルディア州ミラノ出身)
メニュー:イ・クラッシチ(5品)
*
店内へ案内
この日は5組、あとから1組やってきて、計12名。予約なしでも大丈夫だった。会話が弾みまくってウルセー3人組から離れた席へ移動。せっかくの昼どきが台無しになるわえ。
メニューの変更
予約時に伝えておいた、生の甲殻類アレルギー、ボタンエビの件。代わりに、火を通した根菜のサラダアーモンドビネグレットソースをすすめてくる。「魅力的じゃありませんね」カンパチのカルパッチョペペロンチーノ(トウガラシ)に落ち着く。
スターター
スターターでセロリとニンジン等のスープ。この一口で、今回のためにここにしてよかったと、心の底から感じる。しっかりとした酸味、これぞ本場の味。日本人相手だと、味を丸めちゃうでしょ(「酸っぱい」は敬遠のサイン)。ウンザリ。
パンほか
スパゲッティ(乾燥)に見紛う形状のグリッシーニ、ミルクとチーズ入り。やさしい風味。40センチくらいある。掌よりも大きな、ゴマ入りイスフォイヤ(と、きこえた)。薄焼きのクラッカー。どちらも、その途方もない大きさが、客を楽しませる。ジャガイモ入りのパン。強い生地の伸びのみならず、とりわけ皮にジャガイモの風味があり、苦味があるオリーブオイルに浸すと、それだけで立派なつけあわせ。
メニュー変更への対応
ペペロンチーノ(トウガラシ)は、ニコ氏出身のアブルッツォ州らしさを表現している「 アブルッツオ人はドルチェとフルーツ以外のすべてにペペロンチーノを使うとまで言われるほどである(柴田書店 2011:261)」。なおさら、イ・クラッシチで食べなくてドースル。誕生日の食事に前菜として根菜のサラダをすすめてくるとは。不同意を伝えると、魚のチョイスが少なくてと、カンパチを言挙げしてきたんだがなんで言訳してるんだ?自信があるんなら、「ボタンエビの代わりに根菜に火を通したサラダはいかがでしょうか」と、提案するべき。
このサーヴィス女性、客を楽しませる視点が欠落している。要望をかなえることをよろこびとするんではなくて、クレーム対応仕事って態度がありあり。
カンパチのカルパッチョ ペペロンチーノ
で、このカンパチがイタリア料理なんですよ。刺身よりも薄身で、軽い歯ごたえにオリーブオイル、脂の乗った魚でもかろやか。ペペロンチーノが欠かせぬ調味料としてはたらいている。カリカリとした粗塩が振られてて、マリネではなくカルパッチョに仕立ててある意味を悟る。あくまで新鮮に、生でありながら刺身に慣れきった日本人を、イタリアへと連れ出すのだ。グリッシーニにイスフォイヤ、イタリアは手で食べる楽しさにあふれてるな。
スパゲッティ ポモドーロ
ポモドーロ(=トマト)。アルデンテでしっかり小麦を咀嚼させる。これまで見知ってるものよりずっと食べごたえがあり、茹でかた一つとっても異文化。ショーバイにならないと思って日本人は日本人に遠慮しちゃうんだよね、出会いたいのはイタリアローカル。天盛りにも似たハーブとオリーブオイルがチョビッと。しかし、似て非なるアンサンブル。付かず離れず、だがこれなくしては一品料理たり得ぬはたらきをしている。
Akaitoサフランのリゾット ミラノスタイル
リゾットはパスタの仲間。炊くんじゃない、コメの調理。味の正解、調理の正解、一度は本物を食べてみないと。そしてサフランもまた、アブルッツォ州の特産「アブルッツオの産物でとりわけ異彩を放つのはサフランだ(柴田書店 2011:261)」。もちろん日本で生産されている高品質のものを。食べすすめていくうちに、パルミジャーノ(チーズ)がドンドン感じられてくる。さいしょからハッキリ姿を現してたら、バランスとしてクドイんだな。
仔牛のカツレツ ミラノスタイル
皿に、一の字型のカツレツが乗ってるだけ(に見える)。骨付きではなく、ソースもレモンも天盛りもない「レモンをかけないのが正統派の食べ方だと教えられた(平松 2011:79)」。やや洗練が勝ち過ぎてるな。見た目にも寂しいポーション量、まったくクセの感じられない仔牛肉、火入れはほんの少し赤味をのこして。ゾウの耳サイズでもなく、あくまでもスマートな食べ心地。バランスとして、ガツンとくるメイン面(=づら)を期待したいところ。
左端からカットしていくと、ごくごく控えめに、真ん中あたりでカツレツの下に敷かれたマッシュポテトと落ち合う。皿を保護色にして、目に入らなかったのだ。おもむろに姿を現した時点から、カツレツと共に口に入る手筈はお見事。これが皿の余白にヤマモリじゃまったく異なった効果をもたらしてた。一流レストランじゃなくなる。下に敷いてあるゆえ、ソースの役割ともみなせるあたり、快いおどろきがあった。とはいえ、皿には一見カツレツしか乗っておらず、なおさら余白タップリで、メインがケチくさく映ってはいたが。
アーモンドビネグレットソースのミックスサラダ
これでドルチェを残すだけでは、救援を呼びにやらねばならぬと、たっぷりオリーブオイルに浸したジャガイモ入りパンを、計3切れいただく。サラダのソースもきれいにぬぐってお腹の中へ。ハッとするアーモンドビネグレットソース、単体でミニボウル。温かいもの、冷たいもの、温度管理をきちんとサーヴしてくる。あたりまえの一手間、葉物に合わせた緑色の器。ポモドーロの赤に沿う絵付け皿。
ティラミス
ティラミスにはカラメルがバリンと姿を隠している。自立しないカップ仕立て。思い切って甘い、これはカフェクリームを食べさせるもの。その甘さゆえ、コースにキリッとした充実を添えてくれる。こちらに寄り添わず、イ・クラッシチを食べたんだと、向き合う相手との対話が成立しているような。ドルチェまで全部いただいたとの、しっかりとした達成感。メッセージプレートを付けてある。ホワイトチョコに金粉を振ってあるもの。Buon Compleanno(=誕生日おめでとう)。ありがとう!ごく薄くて気が利いてる、この一枚のあるなしが天地の差だと、よけい強く感じさせる。エスプレッソ、そりゃダブルにしますよ。
茶菓子
そして茶菓子に(ホントはカフェ)ボンバ。一口サイズの球形ドーナツ。転げないよう、カスタードクリームで接着してある。いちいちがきちんと処理されてあって、その総体がミシュラン1つ星に輝かせると、納得。お口直しのレモンジュース。卵形(1/2カット)のカップに内側が金メッキされてあり、これもまた明確にレモンと色を揃えている。結果として、どれも印象が鮮やかに心に残る。パン皿とカルパッチョ皿は単なるサイズ違いで、揃いで用意してくるんだなと、まずさいしょに目についたし。
テーブル担当
おかわりエスプレッソはシングルで。そのデミタスカップで、ダブルは並みのコーヒーカップでやってきてたんだと、気づいた。こまめに何度もパン屑を片づけてくれ、パン皿もおかわりといっしょに交換。必要充分量オリーブオイルを注いでくれ、カトラリーの並び替え、念のためもらったリゾットのスプーンを使わなかったにしても、そのまま下げてくれる。気持ちのよいサーヴィスは、何をしにここにやってきたかに応えてくれる。
ミネラル水、イタリアの硬水。これもイタリア産をたずねてるのに、なぜか日本産についてペラペラはじめ出したサーヴィス男性。ともあれ、大瓶で注ぎに来てくれ、自分でボトルから残りを勘案しなくて済む提供方法。
アメニティ
まあ、お手洗いのアメニティはホテルですもの、強みのリネン回収&BVLGARIソープのボトル。で、伝達されておらず、クロークにあずけたカサが忘れられてるウッカリ対応は、数名がかりのもの。
感じのよかったサーヴィスさん
サーヴィス男性の彼、******ホテルからBVLGARIホテルのオープンで移ってきた由。おやおや、ヘッドハンティングですか。貴重な戦力が取り合い。
まとめ
「ショバ代」っていふと、もっと食材に金かけろって聞こえるよな;あまりに一般的な日本語では。だが今回よっく分かったよ、この経験の総体が叶う場として、BVLGARI HOTEL TOKYOが成立・機能しているから味わえたんだと。必要なだけ、予算を割きなさい。

後日談
パンにグリッシーニ、ドルチェに茶菓子までパクついたせいもあり、糖質過剰摂取による体調不良が、次の日まで。異文化理解、痛し痒し。
柴田書店『イタリアの地方料理』(2011年、東京)
平松,玲『イタリア美味遺産:郷土料理を食べ尽くそう![ミラノ→フィレンツェ篇]』(2011年、新潮社)
*
お店:イル・リストランテ ニコ・ロミート(ブルガリ・ホテル・トーキョー内)
監修:ニコ・ロミート氏(アブルッツォ州出身)
ミシュランガイド:1つ星
ヘッドシェフ:マウロ・アロイシオ氏(ロンバルディア州ミラノ出身)
メニュー:イ・クラッシチ(5品)
*
店内へ案内
この日は5組、あとから1組やってきて、計12名。予約なしでも大丈夫だった。会話が弾みまくってウルセー3人組から離れた席へ移動。せっかくの昼どきが台無しになるわえ。
メニューの変更
予約時に伝えておいた、生の甲殻類アレルギー、ボタンエビの件。代わりに、火を通した根菜のサラダアーモンドビネグレットソースをすすめてくる。「魅力的じゃありませんね」カンパチのカルパッチョペペロンチーノ(トウガラシ)に落ち着く。
スターター
スターターでセロリとニンジン等のスープ。この一口で、今回のためにここにしてよかったと、心の底から感じる。しっかりとした酸味、これぞ本場の味。日本人相手だと、味を丸めちゃうでしょ(「酸っぱい」は敬遠のサイン)。ウンザリ。
パンほか
スパゲッティ(乾燥)に見紛う形状のグリッシーニ、ミルクとチーズ入り。やさしい風味。40センチくらいある。掌よりも大きな、ゴマ入りイスフォイヤ(と、きこえた)。薄焼きのクラッカー。どちらも、その途方もない大きさが、客を楽しませる。ジャガイモ入りのパン。強い生地の伸びのみならず、とりわけ皮にジャガイモの風味があり、苦味があるオリーブオイルに浸すと、それだけで立派なつけあわせ。
メニュー変更への対応
ペペロンチーノ(トウガラシ)は、ニコ氏出身のアブルッツォ州らしさを表現している「 アブルッツオ人はドルチェとフルーツ以外のすべてにペペロンチーノを使うとまで言われるほどである(柴田書店 2011:261)」。なおさら、イ・クラッシチで食べなくてドースル。誕生日の食事に前菜として根菜のサラダをすすめてくるとは。不同意を伝えると、魚のチョイスが少なくてと、カンパチを言挙げしてきたんだがなんで言訳してるんだ?自信があるんなら、「ボタンエビの代わりに根菜に火を通したサラダはいかがでしょうか」と、提案するべき。
このサーヴィス女性、客を楽しませる視点が欠落している。要望をかなえることをよろこびとするんではなくて、クレーム対応仕事って態度がありあり。
カンパチのカルパッチョ ペペロンチーノ
で、このカンパチがイタリア料理なんですよ。刺身よりも薄身で、軽い歯ごたえにオリーブオイル、脂の乗った魚でもかろやか。ペペロンチーノが欠かせぬ調味料としてはたらいている。カリカリとした粗塩が振られてて、マリネではなくカルパッチョに仕立ててある意味を悟る。あくまで新鮮に、生でありながら刺身に慣れきった日本人を、イタリアへと連れ出すのだ。グリッシーニにイスフォイヤ、イタリアは手で食べる楽しさにあふれてるな。
スパゲッティ ポモドーロ
ポモドーロ(=トマト)。アルデンテでしっかり小麦を咀嚼させる。これまで見知ってるものよりずっと食べごたえがあり、茹でかた一つとっても異文化。ショーバイにならないと思って日本人は日本人に遠慮しちゃうんだよね、出会いたいのはイタリアローカル。天盛りにも似たハーブとオリーブオイルがチョビッと。しかし、似て非なるアンサンブル。付かず離れず、だがこれなくしては一品料理たり得ぬはたらきをしている。
Akaitoサフランのリゾット ミラノスタイル
リゾットはパスタの仲間。炊くんじゃない、コメの調理。味の正解、調理の正解、一度は本物を食べてみないと。そしてサフランもまた、アブルッツォ州の特産「アブルッツオの産物でとりわけ異彩を放つのはサフランだ(柴田書店 2011:261)」。もちろん日本で生産されている高品質のものを。食べすすめていくうちに、パルミジャーノ(チーズ)がドンドン感じられてくる。さいしょからハッキリ姿を現してたら、バランスとしてクドイんだな。
仔牛のカツレツ ミラノスタイル
皿に、一の字型のカツレツが乗ってるだけ(に見える)。骨付きではなく、ソースもレモンも天盛りもない「レモンをかけないのが正統派の食べ方だと教えられた(平松 2011:79)」。やや洗練が勝ち過ぎてるな。見た目にも寂しいポーション量、まったくクセの感じられない仔牛肉、火入れはほんの少し赤味をのこして。ゾウの耳サイズでもなく、あくまでもスマートな食べ心地。バランスとして、ガツンとくるメイン面(=づら)を期待したいところ。
左端からカットしていくと、ごくごく控えめに、真ん中あたりでカツレツの下に敷かれたマッシュポテトと落ち合う。皿を保護色にして、目に入らなかったのだ。おもむろに姿を現した時点から、カツレツと共に口に入る手筈はお見事。これが皿の余白にヤマモリじゃまったく異なった効果をもたらしてた。一流レストランじゃなくなる。下に敷いてあるゆえ、ソースの役割ともみなせるあたり、快いおどろきがあった。とはいえ、皿には一見カツレツしか乗っておらず、なおさら余白タップリで、メインがケチくさく映ってはいたが。
アーモンドビネグレットソースのミックスサラダ
これでドルチェを残すだけでは、救援を呼びにやらねばならぬと、たっぷりオリーブオイルに浸したジャガイモ入りパンを、計3切れいただく。サラダのソースもきれいにぬぐってお腹の中へ。ハッとするアーモンドビネグレットソース、単体でミニボウル。温かいもの、冷たいもの、温度管理をきちんとサーヴしてくる。あたりまえの一手間、葉物に合わせた緑色の器。ポモドーロの赤に沿う絵付け皿。
ティラミス
ティラミスにはカラメルがバリンと姿を隠している。自立しないカップ仕立て。思い切って甘い、これはカフェクリームを食べさせるもの。その甘さゆえ、コースにキリッとした充実を添えてくれる。こちらに寄り添わず、イ・クラッシチを食べたんだと、向き合う相手との対話が成立しているような。ドルチェまで全部いただいたとの、しっかりとした達成感。メッセージプレートを付けてある。ホワイトチョコに金粉を振ってあるもの。Buon Compleanno(=誕生日おめでとう)。ありがとう!ごく薄くて気が利いてる、この一枚のあるなしが天地の差だと、よけい強く感じさせる。エスプレッソ、そりゃダブルにしますよ。
茶菓子
そして茶菓子に(ホントはカフェ)ボンバ。一口サイズの球形ドーナツ。転げないよう、カスタードクリームで接着してある。いちいちがきちんと処理されてあって、その総体がミシュラン1つ星に輝かせると、納得。お口直しのレモンジュース。卵形(1/2カット)のカップに内側が金メッキされてあり、これもまた明確にレモンと色を揃えている。結果として、どれも印象が鮮やかに心に残る。パン皿とカルパッチョ皿は単なるサイズ違いで、揃いで用意してくるんだなと、まずさいしょに目についたし。
テーブル担当
おかわりエスプレッソはシングルで。そのデミタスカップで、ダブルは並みのコーヒーカップでやってきてたんだと、気づいた。こまめに何度もパン屑を片づけてくれ、パン皿もおかわりといっしょに交換。必要充分量オリーブオイルを注いでくれ、カトラリーの並び替え、念のためもらったリゾットのスプーンを使わなかったにしても、そのまま下げてくれる。気持ちのよいサーヴィスは、何をしにここにやってきたかに応えてくれる。
ミネラル水、イタリアの硬水。これもイタリア産をたずねてるのに、なぜか日本産についてペラペラはじめ出したサーヴィス男性。ともあれ、大瓶で注ぎに来てくれ、自分でボトルから残りを勘案しなくて済む提供方法。
アメニティ
まあ、お手洗いのアメニティはホテルですもの、強みのリネン回収&BVLGARIソープのボトル。で、伝達されておらず、クロークにあずけたカサが忘れられてるウッカリ対応は、数名がかりのもの。
感じのよかったサーヴィスさん
サーヴィス男性の彼、******ホテルからBVLGARIホテルのオープンで移ってきた由。おやおや、ヘッドハンティングですか。貴重な戦力が取り合い。
まとめ
「ショバ代」っていふと、もっと食材に金かけろって聞こえるよな;あまりに一般的な日本語では。だが今回よっく分かったよ、この経験の総体が叶う場として、BVLGARI HOTEL TOKYOが成立・機能しているから味わえたんだと。必要なだけ、予算を割きなさい。

後日談
パンにグリッシーニ、ドルチェに茶菓子までパクついたせいもあり、糖質過剰摂取による体調不良が、次の日まで。異文化理解、痛し痒し。
柴田書店『イタリアの地方料理』(2011年、東京)
平松,玲『イタリア美味遺産:郷土料理を食べ尽くそう![ミラノ→フィレンツェ篇]』(2011年、新潮社)
タグ :しょくぶつ
2025年04月03日 Posted by Tom Motsuzai at 11:00 │Comments(0)
作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせ
町田市で作曲家やってるTomです。毎月開催の、作曲を学ぶ&楽しむ会のおしらせ。
第59回。しめきりは3月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-59
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は8分の6拍子、ラ短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
音楽と、ことば。
応募作品には、かならずコンセプトを添えてもらっている。
タイトルだけでは、そのコンテクストがわからないから。
それは皮肉なのか、真正面から受け止めていいのか。
具体的な体験からのものか、たんなるおもいつきか。
作者の求める、タイトルへのかかわりかたを、コンセプトで説明してもらふ。
テクストとちがって、音は、たんなる抽象現象。
だから、「untitled(=無題)」と名づけられた音楽作品は、ごくごくわずか。
ホントはあること自体、信じられない事態といいたいけれども。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
第59回。しめきりは3月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-59
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は8分の6拍子、ラ短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
音楽と、ことば。
応募作品には、かならずコンセプトを添えてもらっている。
タイトルだけでは、そのコンテクストがわからないから。
それは皮肉なのか、真正面から受け止めていいのか。
具体的な体験からのものか、たんなるおもいつきか。
作者の求める、タイトルへのかかわりかたを、コンセプトで説明してもらふ。
テクストとちがって、音は、たんなる抽象現象。
だから、「untitled(=無題)」と名づけられた音楽作品は、ごくごくわずか。
ホントはあること自体、信じられない事態といいたいけれども。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
タグ :勉強会
2025年03月06日 Posted by Tom Motsuzai at 11:00 │Comments(0)
作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせ
町田市で作曲家やってるTomです。毎月開催の、作曲を学ぶ&楽しむ会のおしらせ。
第58回。しめきりは2月28日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-58
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ド短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
はやるきもちと、中途の作品。
今回とりくんでみたことに、その如何を知りたくて。
出してきた当人も、それが生煮え状態だと、わかっているが。
たしかに、生煮えだと、評価はしにくい。ホントは、もっとやれたのかもしれないし。
だが、それをやってみたかった意思のほうが、大切。
あたかも、走り出してから、走り方をあれこれ勘案してるみたいな。
創作では、どこかに衝突する危険はありません。ただし、行き詰まりはある、、。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
第58回。しめきりは2月28日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-58
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ド短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
はやるきもちと、中途の作品。
今回とりくんでみたことに、その如何を知りたくて。
出してきた当人も、それが生煮え状態だと、わかっているが。
たしかに、生煮えだと、評価はしにくい。ホントは、もっとやれたのかもしれないし。
だが、それをやってみたかった意思のほうが、大切。
あたかも、走り出してから、走り方をあれこれ勘案してるみたいな。
創作では、どこかに衝突する危険はありません。ただし、行き詰まりはある、、。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
タグ :勉強会
2025年02月10日 Posted by Tom Motsuzai at 11:00 │Comments(0)
パレスチナとサボテン
私たちパレスチナ人は、サボテンのようなものです。
水を我慢し、空腹を我慢し、封鎖を我慢する。
私たちにも生活があり、文化があり、人生を愛している日常を送っている。
ライエッド・イサ(1975-)
https://sakima.jp/exhibition/.assets/exhibits220422-0613_v2.pdf
*
ライエッド・イサ氏は画家。画家グループ「エルティカ」の一人として、2019年に仲間2人と来日。日本各地を作品展示とともに、お話しして回る。
現在は、イスラエルのガザ侵攻・破壊の余波で、テント生活を強いられている。
*
サボテンは、実が食用になり、パレスチナでは広く親しまれている。また、そのトゲは不屈の象徴でもあるとも。
さふいえば、中東を旅した、2002年4月のクドゥス(=エルサレム)。サボテンの実を、路上で販売しているのをみかけた。
*
だから、彼の描くサボテンは、単なる手近にある静物ではない。
生き抜く魂そのものだ;ガザを「所有する」との、一国の大統領の放言がまかりとおる世の中では。
タグ :アラブ
2025年02月07日 Posted by Tom Motsuzai at 11:00 │Comments(0)
作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせ
町田市で作曲家やってるTomです。毎月開催の、作曲を学ぶ&楽しむ会のおしらせ。
第57回。しめきりは1月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-57
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ラ長調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
作品から作品へのつながり。
ひとつできあがると、ひとつ手が離れると。
「それ」は、手の内にはいる。
さらにのびのびつづけてもいいし、意にかなわなかったと、も一度とりかかってもいい。
またはサッパリわすれて、ぜんぜんちがふことをはじめてもいい。
それでも、上述の条件すべてに共通するのは、直近の作品が、これから取組む作品のきっかけであること。
この意味で、書いたこと/ものは、なくならない。
なにかが手元から失せても、持ってた体験は奪えないのだ。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
第57回。しめきりは1月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-57
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ラ長調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
作品から作品へのつながり。
ひとつできあがると、ひとつ手が離れると。
「それ」は、手の内にはいる。
さらにのびのびつづけてもいいし、意にかなわなかったと、も一度とりかかってもいい。
またはサッパリわすれて、ぜんぜんちがふことをはじめてもいい。
それでも、上述の条件すべてに共通するのは、直近の作品が、これから取組む作品のきっかけであること。
この意味で、書いたこと/ものは、なくならない。
なにかが手元から失せても、持ってた体験は奪えないのだ。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
タグ :勉強会
2025年01月12日 Posted by Tom Motsuzai at 10:00 │Comments(0)
『まなざしを上げて』再演のもよう
町田市で作曲家やってるTomです。標記の件、動画にまとめました。
*
演奏後に、作曲者が感想を、ひとくさり。
字幕付きだが、以下に掲載。
音楽は非暴力と、非常に結びつきがあると思うんですね。
楽器は手荒に扱うと壊れちゃうし、
そうして歌ってくれなくなっちゃうと困るのは自分ですよね。
ですから、いい音楽をいい演奏で聴いていただくだけで
一石二鳥っていうかね、
非暴力のメッセージ、反戦のメッセージっていうものが
そのまま受け取れるんじゃないか。
そんなことを改めて、立木さんの演奏を聴いて思いました。
皆さんも楽しんでいただけましたかね。ありがとうございます。
*
演奏後に、作曲者が感想を、ひとくさり。
字幕付きだが、以下に掲載。
音楽は非暴力と、非常に結びつきがあると思うんですね。
楽器は手荒に扱うと壊れちゃうし、
そうして歌ってくれなくなっちゃうと困るのは自分ですよね。
ですから、いい音楽をいい演奏で聴いていただくだけで
一石二鳥っていうかね、
非暴力のメッセージ、反戦のメッセージっていうものが
そのまま受け取れるんじゃないか。
そんなことを改めて、立木さんの演奏を聴いて思いました。
皆さんも楽しんでいただけましたかね。ありがとうございます。
タグ :自作解説
2024年12月26日 Posted by Tom Motsuzai at 10:00 │Comments(0)
作曲を学ぶ&楽しむ会のお知らせ
町田市で作曲家やってるTomです。毎月開催の、作曲を学ぶ&楽しむ会のおしらせ。
第56回。しめきりは12月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-56
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ミ短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
ゼロにすること、わすれること。
それまでやってきたことが、あらたな作品のじゃまになることも。
なにか、とりかかろうとすると、「それ」が、あたまをもたげてくる。
だったら一度、あたまからおいはらえばいい。
やったことのない、とおったことのない道を、あらたに見出すのはだれか。
「その手があったか!」と、だれかがみつけるまえに。
ぜひそれは、自分自身でありたい。
創作リストを、積極的に忘れよう。
とはいえ、漫然とおなじことをくりかえしてしまわないように(ドキッ)。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
第56回。しめきりは12月31日。
https://sakkyoku.ensemble.fan/correction-56
2小節の旋律課題を出します。それを利用して、16小節ていどの小品にまとめてくらはい。編成は自由。譜面の提出に、作品のコンセプトを添えてもらって。譜面は浄譜したものでも、手書きを写メ(←死語、、)したものでも。
今回の旋律は4分の4拍子、ミ短調。

メロディを8小節にかきのばして、かんたんな伴奏をつけたていどでもオーケイ。
*
ゼロにすること、わすれること。
それまでやってきたことが、あらたな作品のじゃまになることも。
なにか、とりかかろうとすると、「それ」が、あたまをもたげてくる。
だったら一度、あたまからおいはらえばいい。
やったことのない、とおったことのない道を、あらたに見出すのはだれか。
「その手があったか!」と、だれかがみつけるまえに。
ぜひそれは、自分自身でありたい。
創作リストを、積極的に忘れよう。
とはいえ、漫然とおなじことをくりかえしてしまわないように(ドキッ)。
*
応募作品に、寸評つけます。そのあとZOOMを使った質問会を、任意参加で開催(別料金)。
それではあそびのつもりで、まずは上掲のメロディを弾いてみよう。
タグ :勉強会